雑誌「ランナーズ」に、「マラソンは脳力」という特集がありました。
走っている最中に「調子が悪い」「脚が重い」といったネガティブな意識が生まれると、それがフィジカルにも影響して実際に調子が悪くなってしまう経験はないでしょうか?

言い換えるなら、気の持ちよう(=脳)で走りも変わる、ということですね。
このコンテンツでは、走りを助ける脳の使い方をまとめています。
(雑誌ランナーズ 2016年03月号(Amazon)8~9ページを参考にしています)
[cc id=9377 title=”レスポ横長”]
走りを助ける能力の上げ方 4つのポイント
走りをサポートする考え方をする=脳力を上げるにはどうすれば良いのでしょうか?
東京工芸大の山本正彦准教授は、以下のようなポイントを挙げています。
1 前半からポジティブであるべき
力を発揮するには、体力が限界に達する前からポジティブでいる必要があります。練習不足を自覚していても、目標をあえて低くしたり、どれくらいのタイムで走れるかな?と楽しむ気持ちで前向きになりましょう。
2 チョイきつでも話せる
前半から飛ばしすぎるとグリコーゲンの消費が激しくなります。グリコーゲンがなくなると、脳のエネルギーもなくなって脳力を活かせなくなります。「少しキツいけど話せる」ペースをキープしましょう。

3 市民ランナーは脳がストップをかける
トップ選手は少々の痛みでも走れますが、多くのランナーは疲労感や痛みを感じると失速してしまうことが多くなります。普段きついトレーニングをしていないので、身体を限界まで動かす前に脳がストップをかけるのです。
また、レース中は脳も疲労し、身体へ命令を出せなくなったり意欲が落ちることもあります。
4 脳をいかにだますか
レースの最後まで身体を動かし続けるには、「楽しい」や「嬉しい」といった気持ちを持ち、脳に「辛くない」と思わせることが大切です。また、脳のストッパーを外すには、脳を負荷に慣れさせるだけの練習が必要です。
山本准教授が勧めるのは、5kmや10kmなど短い距離のレースや練習です。比較的ペースが速くなるので、より多くの情報が目から入り、脳のトレーニングになります。これはレースで特に疲れる右脳(情報を処理する働きがある)の鍛錬になります。
また、息が上がる苦しさを経験することは、リミッターを外すことにもつながります。川内優輝選手が倒れるほど追い込めるのも、1500mや駅伝といった短い距離にも挑戦しているから、と山本准教授は考えています。
[cc id=12262 title=”アドセンス30-25″]
脳力を開発する余力の大きさ チェック項目
脳をどれほど開発できるかをはかるには、いくつかの基準があります。
以下のチェック項目に当てはまる数が多いほど、脳力を開発する余地が大きいと考えられます。
■日常編(練習編)
・ジョギング以外はほとんど運動しない
・いつも一人で走っている
・走るところは整備された平地
・サプリメントはなんとなく飲む(レース編と共通)
■レース編
・途中どこかが痛くなるが、レース後はそこまでダメージがない
・つい苦しい顔をして走ってしまう
・毎回定める目標は一つだ
・応援を見ている余裕はない
・あまり給食は食べない
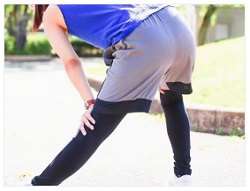
次のページに続きます。
[cc id=9377 title=”レスポ横長”]

